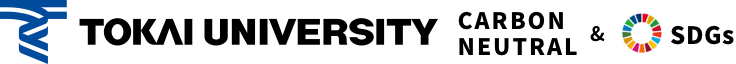- 研究紹介
公開日:2025/03/17
【インタビュー】フィンランドが世界一サスティナブル(持続可能)な国である秘密とは

文化社会学部北欧学科
柴山由理子准教授
フィンランドは、国連と連携している国際的研究機関「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」がまとめた報告書「持続可能な開発レポート2022」で世界1位にランキングされ、福祉の充実度や幸福度ランキングでも常に高い評価を受けています。その理由や背景について、フィンランドの政治が専門の柴山由理子准教授(文化社会学部北欧学科)に伺いました。

―各種のランキングでフィンランドが上位に入る理由はなぜでしょうか?
市民の中で「自分たちがこの国や社会の担い手なのだ」という意識がとても高いことがあげられると思います。政治の透明性が高く、市民の声が政治に反映されやすいことも特徴です。
フィンランドは国土こそ広いものの、人口は550万人しかいません。首都のヘルシンキでも人口は65万人ほど。ロシアやスウェーデンといった大国に常に脅かされてきたうえ、大きな産業がない貧しい時代が1960年代頃まで続きました。小国が生き抜くためには、物事を現実的に考えて、新しい考えも積極的に取り入れていかなければならなかったのです。さらに、キリスト教のプロテスタンティズムの「一人ひとりの力をあわせて、よりよい社会をつくる」という思想が社会全体に浸透していることも大きく影響しているかもしれません。
―フィンランドではいつ頃から環境政策が意識されるようになってきたのでしょうか?
環境問題への関心が高まったのは1970年代から1980年代にかけてですが、大きな転機は、1995年に環境政策の充実を掲げる「緑の党」が政権与党に入ったころからだと考えています。気候変動対応や環境政策が、国政に大きな影響を与えるようになりました。
その後、東欧諸国からの越境汚染や林業・製紙業による湖や川の汚染への関心が高まっていきます。 IPCCが発表した1.5度特別報告書の反響で、2019年の国政選挙では環境政策が大きな争点になりました。
この問題に対して、生活に根差しながら現実主義的に対応しているのもフィンランドの特徴です。天然資源がほとんどないため、エネルギーを確保するために原子力発電所も積極的に活用しています。ごみの分別も日本よりキチンと定められていないのが一般的です。そうした政策も、賛成派と反対派が対話しながら現実的な施策を組み立てており、社会情勢や国際環境を見据えながら折々に変化させています。
また、「循環型社会」や「持続可能な社会」という理念を産業や政策と結び付けて、社会全体の仕組みをデザインするという思考方法が広く取り入れられている点も興味深いところです。
―これからの日本にとって参考になることはありますか?
フィンランド社会では、「TALKOOT(タルコート)」という考え方が強く残っています。日本語では「共助」と訳せるのですが、引っ越しや部屋のリノベーションも友人や隣人が協力し合ってやってしまいます。「日本のようにサービスを購入しなくても、みんなで集まって取り組む方法がある」と思うほどです。
そうした主体性や自己選択、自己決定の姿勢は見習えるところがあると思っています。フィンランドは「世界一幸福度の高い国」と評されます。でも私は、身の回りのさまざまな課題について自分で考え、納得したうえで決断をしている人が多い「納得度の高い国」なのではないかと考えています。
日本では、少子高齢社会が進展し、どんどん人口が減ってきています。そうした中で、「質としての豊かさを保ちつつ納得度の高い社会」をどう実現していくかが大きな課題です。そうした社会を実現するために、フィンランド人の社会に対する姿勢から学べることは多いのではないでしょうか。
しばやま・ゆりこ
早稲田大学社会科学研究科博士課程後期を満期退学。2007年からGollaOyに勤務し、Vice President of Sales & Marketingなどを務める。18年4月より現職。専門は比較政治学、フィンランド・北欧の地域研究。