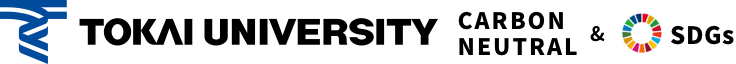- 研究紹介
公開日:2025/02/21
【インタビュー】電池開発がカーボンニュートラル実現の肝

工学部応用化学科
松前義治先生
カーボンニュートラル社会を実現するために世界中で新たな技術の開発が進められています。そのなかで、もっとも重要な分野の一つが「電池開発」です。高性能で安全な蓄電池があれば、電気をより効率的に利用することもでき、再生可能エネルギーが活用できる領域も広がります。そんな電池技術開発の今と未来について、工学部応用化学科の松前義治先生に聞きました。
―今、世の中を支えている電池はどんなものですか?
エネルギーを貯めるためによく活用されているのが「リチウムイオン電池」ですね。今ある蓄電池のなかで、最も効率よくエネルギーを貯められる電池として、携帯電話はもちろん、家電製品や自動車など幅広い領域で使われています。
一方で、材料に「有機溶媒」という燃えやすい物質を使っているという点で安全性の問題も抱えています。また、リチウムやコバルトといったレアメタルが使われているのも課題です。リチウムは中国や南米、アメリカなど限られた地域でしか取れませんし、コバルトは全世界の埋蔵量を足しても、将来の需要を賄えないと言われています。
―今どんな研究が注目されているのでしょう?
より安全に・幅広く使えるようにするため、有機溶媒やレアメタルに頼らない代替技術の開発が注目されています。有機溶媒を燃えづらい固体に置き換えた全固体電池や、リチウムやコバルトの代わりにより身近にあるナトリウムや硫黄を使った電池の研究も進んでいます。
安価で大容量、かつ安全にエネルギーを蓄えられる電池が開発できれば、再生可能エネルギーの普及も一気に進みますし、いつか来る石油の枯渇にも耐えられます。そのために、世界中の研究者が必死に研究しているのが現状です。
―先生の研究室ではどんな研究をされていますか?
私の研究室では、安価に電極を作る技術の開発に取り組んでいます。最近では、電子レンジに使われるマイクロ波を使って、正極に使う硫化リチウムを合成する技術の開発に成功しました。硫黄は、地球上の埋蔵量も豊富で、石油資源を生成する過程でも大量に出る物質なのですが、硫黄から硫化リチウムを合成するためには大量の時間や熱エネルギーが必要だったため、利用が難しかったのです。それが電子レンジを使って5分で作れるようになりました。そのほかにも、ナトリウムやカリウムを使って電極に使える材料を合成する技術の研究も進めています。
―先生の将来の夢をお聞かせください
硫化リチウムを使ったリチウム硫黄電池の実用化などを通して、より安価な電池の開発に貢献していきたいと思っています。硫黄系の材料は何より安価なうえ、大型化しやすく軽量であるという特徴も持ち合わせています。これが実現できれば、再生可能エネルギーの活用も一気に広がると期待しています。
【コラム 現代化学の基礎を作った電池の発明】
私たちの生活に欠かせない電池の原型は、1800年にイタリアの物理学者ボルタによって発明されました。その後、ボルタの電池を使って、イギリスの科学者デービーが水溶液を電気分解してナトリウムやカリウムなどの元素を発見。現代の化学の基礎をつくったのも、電池だったのです。
まつまえ・よしはる
東北大学工学部化学・バイオ工学科卒業。東北大学大学院環境科学研究科環境科学専攻博士課程修了。横浜国立大学大学院工学研究員特任助教を経て、2018年9月に工学部応用化学科に着任。専門は、ナノテク・材料、エネルギー化学、電気化学など